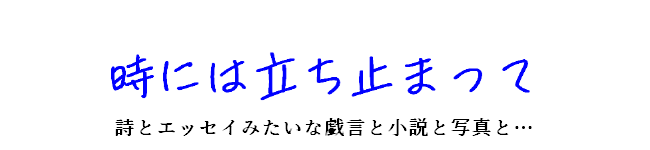帰宅したことの報告で伯父の家へ電話して以降、伯父の家のことも智子のことも次第に気にかけなくなっていく。日々の仕事に追われることも原因の一つだけど、元々目の前のことだけしか処理できない人間だから、何かを処理していくたびに心には新たなことが上書きされ、自分では大事だと思っていることまで心の中で埋もれていく。
翌年の春には智子は地元の中の上ランクの公立高校に合格したと、母から聞いた。
僕は七月に昇格試験を受けたが、入社同期三〇名のうち合格したのは三名だけ、もちろん僕の名前は入っていなかった。この年の夏は人員が極度に不足した状態に陥っており、オートバイに跨るの公休日を含む通勤の時だけで、仕事に忙殺されていた。もちろん昨年智子と約束した事なんて頭からきれいさっぱり抜け落ちていた。それどころか新しい彼女ができたので、仕事の合間を縫ってデートの時間を作ることが大変な状態で、智子のことを考える余裕なんてなかったし。
結局僕は目の前のことだけに注力して、全体を俯瞰して先々のことを考える能力が欠乏していた。今は目の前のオートバイ、今は目の前の女性、今は目の前の仕事、目の前のことを処理することしか頭になかった。処理するたびに僕の智子への気持ちに上書きされていき、いつしか存在自体が見えなくなっていく。
「直樹、明日兄ちゃんと智子や香織が家に来るらしいんだけど、何か用事あるの?」
仕事が終わり家でゆっくりしている時に、母からの電話で智子たちが来ることを知った。伯父が高校野球の全国大会へ出場している学校の中で、どうしても生で観たい試合があるらしい。
「明日は午前中に仕事が終わるから、それから家へ行くよ」
そう話して電話を切り、大慌てで会社へ電話して午後からの残業をキャンセルした。
翌日の昼過ぎ、仕事を終えると実家へ直接向かった。伯父と香織は野球場へ行ったらしく、母と智子だけが家にいた。
「直くん、久しぶり!」
「智子は野球場へ行かなかったんだ」
「うん、松井くんがホームランを打つところは見てみたいけど、直くんが来るって聞いたから行かなかったんだ」
「そうか、僕はゴジラより強かったんだね。それはそうと、香織って野球に興味なんてあるの? スポーツ全般にあまり興味がなさそうなのに」
「アルプススタンドのブラスバンドに興味があって、それを見に行ったの」
「なるほど、香織は音楽家だもんな」
「直くんって、松井くんよりずっと年上なんだよね、なんだか不思議な気がする……」
「松井って二年生だよね、智子と一つしか変わらないんだ」
「それもなんだか不思議な感じ。高校野球をしている人たちってお兄さんって感じだったのに、今は自分が高校に通っているんだもん」
「直樹、お昼は何か食べたの?」
「会社で食べてきたよ」
「じゃあ、買い物に行ってくるからお留守番よろしくね」
母は買い物へ出かけ突然智子と二人きりの時間が訪れた。昨年夏に会った時以上に女性っぽくなっている。親戚だから、『いとこ』だから理性が働いて止められているけど、そうじゃなきゃ止められる自信がない。たった一年でこれほどまでに変わるんだな。
「ねえ、直くん。今年の夏はうちへ来る予定は立てていた?」
「うーん、立てていなかった……、何かと忙しくて、なかなかね……」
「やっぱり……。また何年か会えない気がして、お父さんに連れて来てもらったの」
「ごめんね……」
「それで、彼女とは上手くいっているの?」
「前の彼女とは秋に別れた。で、今は別の女性と付き合っている」
「そうなんだ……。新しい彼女か……。今度は仲良くしてるの?」
「うーん、前とあまり変わらないような気もする……」
智子と少し話をしただけで、僕はちょっと違和感を覚えた。
今度の彼女は僕が好きで付き合っていると思っていたのに、智子と少し話しただけで彼女への気持ちが急速に冷めていく気がしたのです。ただの浮気性なのかもしれない、ただ優柔不断なだけかもしれない。子供と同じで目移りが激しいのかもしれない。でも智子と話をしていると昨年の夏にオートバイの後ろに乗せて走ったこと、目に涙を溜めてうるうるする智子に引き込まれそうになったことが、埋もれていた記憶の中からよみがえって頭の中を駆け巡りだす。
「直くん、明日はお仕事? それともデート?」
「お昼過ぎまで仕事で、あとは予定はないよ」
「じゃあ、明日もいっしょにいられる?」
「うん、大丈夫だよ」
「直くん、明日はお洒落なカフェに連れて行ってほしいんだけど……」
「カフェかあ、じゃあ西の方にでも行く?」
「うん!」
「じゃあ明日は一年ぶりにオートバイに乗る? 電車で行くよりいいよね?」
「また乗せてくれるんだ! やったー!」
この日は家で智子といろいろ話をして、伯父と香織が甲子園から帰ってくる前の夕方に帰宅した。明日の朝は仕事が始まるのが早いし、それに、デートを断らなきゃいけないから。
「もしもし、明日だけど急に残業になっちゃって……」
「仕事なの? 最近あまり会ってくれないし……、浮気しているんじゃない?」
夜、彼女の家に電話した僕は仕事だとウソをついた。GWを過ぎたころから彼女と会うのが面倒というか億劫に感じることがよくあり、いろいろと理由をつけてはデートをキャンセルしていた。ただ彼女に指摘された浮気なんてことは一度もなく、一人でただオートバイを転がしていただけ。明日のデートのキャンセルが初めての浮気によるものと言えるかもしれない。
昨年の夏、智子に言った、
〝今って言うか……、今まで本当に好きになった人っていないかも……〟
今の彼女もやっぱり僕は好きではなかったみたいだし、好きにもなれなかった。そして僕の本当の気持ちが心の奥底から浮かび上がって姿を現し、僕自身もそのことに気付いた――。
一三時過ぎに仕事が終わり、職場から直接オートバイで実家にやってきた。
「智子、お待たせ!」
「直くん、もうちょっと遅くなるのかと思ってたよ」
「職場から直接オートバイで来たら一〇分ちょっとで着くから」
「あっ、私、ヘルメットがないよ……」
「もう一個持ってきたから」
去年の夏、伯父の家へかぶって行ったヘルメットを手渡すと、
「これ、前に直くんがかぶっていたヘルメットだよね」
「そうだよ」
「そうだよね、見覚えがあるもん……」
「直樹、どこまで行くのかは知らないけど、事故だけは起こさないようにね」
「うん、後ろに人を乗せてるときは慎重に走るから」
「直くん、行こ!」
「うん」
家の前に止めていたオートバイにまたがり、西へと走らせた。
「直くん……、すごいおしゃれな店だけど、いつもこんなお店でデートしてるの?」
「おしゃれなお店は苦手だから初めて来たんだ、ちょっと場違いな感じがするよ……」
「そうなんだ、私もこういうお店は初めて。何だかいい感じのお店ね」
「良かった、智子に気に入ってもらえて」
「ところで、直くん。彼女には何と言ってデートを断ったの?」
「えっ?」
「わかるよ、直くんが考えることくらい。私のためにデートを断ったんでしょ」
「まあなあ……」
「無理しなくてもいいのに。もしも直くんがだれかと結婚したって私と直くんは『いとこ』同士、それは一生変わらない。私が他のだれかと結婚したって直くんとはずっと『いとこ』同士。そこは何があっても変わらないんだから、直くんがしたいようにしなきゃ」
「無理はしていないんだ、本当に。僕の中で優先したいほうを選んだだけだから」
「ひょっとしたら、私って直くんの邪魔してる?」
「いいや」
「そうかなあ、私が直くんと彼女との溝を深くしている気がして……。私が来なかったら、直くんは私のことなんて全然考えなかったでしょ? 私が来ていなかったら、今ごろ彼女とイチャイチャしているだろうし……。前の彼女とだって……」
「僕は邪魔されているとは思っていないし、正直に言って、今の彼女のことも自分の本心ではどう思っているのかわからなくて……」
「やっぱり私が邪魔しているから、直くんの気持ちが揺らいでいるんだよ。私と会わなかった一年くらいの間は、私のことなんて全然考えることなんてなかったでしょ?」
「たしかにそうだね……」
「やっぱり邪魔しているんだよ、私が……」
邪魔しているんじゃない、智子が僕の本心を呼び起こしてくれるんだよ。付き合ってはいても少しずつ何だか違うような気がしてきて、智子の顔を見るとその違う部分がはっきりとわかるんだ。智子に会えない間に自分自身の気持ちが見えなくなり、そして失っていく。智子に会うとその失ったものがまた浮かび上がってくるんだ。
本当はそこまで言い切ろうと思った。頭ではそこまで考えた。でも言葉としては出てこなかった。智子は親戚だから、智子は『いとこ』だから、そんな縛りによって僕の自由を阻止されてしまう。今の僕の智子への思いは「好き」だ、それは間違いない。それが『いとこ』として好きなのか、一人の「女性」として好きなのかもわからない。いや、縛りによって僕の心がわからないふりをしている。ふりをしているからはっきりと言葉に出して言えない。
智子は僕のことをどう思っているのかな。やっぱり親戚の『お兄ちゃん」として好きなのかな。まさか一人の男性として僕のことを見てはいないだろう。
「智子が邪魔しているとは思えないよ。本当に邪魔だと感じていれば、逆に今日は智子とは会っていない。昨日だって実家には行かず家でのんびりとくつろいでいたよ」
「直くん、直くんは私のことどう思ってる?」
「昔は大嫌いだった。智子が生まれて伯父ちゃんを盗られた気がしたからね」
「えっ? 大嫌いだったんだ……」
「僕の勝手な思いすごしだとわかってからは、全然変わった。今は好きだよ」
「それは『いとこ』としてだよね……」
僕は『いとこ』としてなのか「女性」として好きなのか、自分でもはっきりしないと言おうとしたが、智子の聞き方に「女性」として好きだと言ってはいけないような気がして、
「『いとこ』としても大好きだよ」
「そうだよね、『いとこ』としてだよね。私もそう考えるようにしよう……」
智子の答えを聞いて「女性」としても好きだよと言い直そうと思ったけど、全然言葉として出てこなかった。僕の考えや思いを支配する領域は『親戚だから』『いとこだから』という見えない鎖で縛られている。大好きだった伯父の子供と男女の仲になるだなんて不謹慎だろ、そんな思いが強く支配しているのかな。
「『いとこ』同士か。『いとこ』じゃなかったら、ちょっとは何かが違っていたのかな」
「でも『いとこ』同士でも結婚はできるんだよ」
「前に智子が言ってたよね、僕も本屋さんへ行って六法全書で確認したよ、『いとこ』は結婚できることを」
「『いとこ』同士は結婚できるんだもん、ふつうにお付き合いしてもいいってことよね」
「そういうことになるね。もしも僕と智子が付き合うことになったら、智子のお父さんやお母さんも、僕の母も仰天するだろうね」
「びっくりはするだろうけど……、直くんはそういうのをやっぱり気にする?」
「気にするかと言われたら、やっぱり気になるかな……。もしも……、もしもだけど、僕と智子が付き合うとなれば、関西と広島という二人の距離と『親戚』とか『いとこ』っていうのも引っかかるかな」
「直くんは『いとこ』ということが引っかかるのか……」
「でも本当に好きになって付き合うとしたら、『いとこ』という縛りなんて関係なくなるとは思うよ。告白して付き合うまでが大変かな……」
「私は全然気にしない。好きになってお付き合いして、そして結婚できるのならば。それほど好きでもない人と付き合ったり結婚することを思えば、大好きになった人が『いとこ」だったら、私は間違いなく『いとこ』を選ぶ。ううん、『いとこ』という関係性を投げ捨てて男性として見ていくもん」
「たしかに、自分の気持ちを優先させるべきだもんな、僕みたいな付き合い方をしていてはダメだよな……」
「でも、直くんには好きかそうでもないかは別にして、現に付き合っている彼女がいるから」
そう、僕には彼女がいる。でも智子と会うことで本気ではない、本当は好きでもないのに付き合っていることに気付かされる。
僕は智子のことが好きだ、親戚の女の子としてではなく一人の女性として好きだ。でもしばらく顔を見ずに生活しているうちに、その気持ちが再び埋もれていく。埋もれてしまった隙に別の女性と何かが違うと思いながら関係を持ち、さらに自分の本心に蓋をしてしまう。
今すぐに智子に告白するほうが良いと思うのですが、いざ口にしようとすると僕を縛るものがさらに強くなって僕を雁字搦めにしてしまう。
智子は『いとこ』として僕が好きなだけ、そして告白してフラれること以上に『親戚』に恋愛感情を抱く危ない人と思われて、『いとこ』としても会えなくなるかもしれない、そんな不安によって僕の心が阻止されてしまい口に出せなくなってしまう。
後になっていっぱい言い訳じみたことばかり考えているけど、結局はただの意気地なし。
智子の気持ちだってわかっているのに、自分で自分を縛って勝手に動けなくしているだけの意気地なし。
結局告白することなくお店を出て、オートバイにまたがり実家へと舞い戻った。