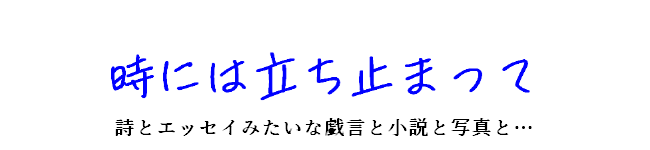小学二年生になった一九七六年の夏休み、今までは少しでも早く〝田舎〟へ行きたかったのですが、今は訪れたところで誰にも相手にされないことがわかっていたし、退屈な夏をすごすくらいならば自宅に残って同級生たちと遊ぶほうがいくらか楽しい。だから〝田舎〟へは行きたくはないと懇願したのですが聞き入れてもらえず、夏休みに入ってすぐに父と母、三歳年下の弟の徹とおると新幹線に乗って〝田舎〟へ行き、僕以外は一泊だけしてすぐ自宅へ帰ってしまい一人ぼっちの夏休みをすごしました。僕が本気で〝田舎〟はイヤだと訴えているとは思わなかったのでしょう。なにせ物心が付いた時からずっと、伯父とすごすことを楽しみにしていたのですから。
週に一度は伯父も〝田舎〟へ顔を出すのですが、やってきたところで僕がもっと小さかったころと智子の比較話だけをして帰っていくので、ただただ伯父を智子に盗られたという気持ちを強めるだけでした。
祖母は畑仕事に精を出しあまり僕と遊ぶことはありませんが、その日は祖母の通院の日だったので、僕は祖母といっしょに駅前までバスで出かけました。小学二年生の僕を一人で留守番させるのは忍びないとでも思ったのでしょう。ただ僕は病院まで連れて行ってくれるものと思っていたのですが、祖母が通う病院はさらに電車で一駅先にあるので連れて行ってもらえず、駅近くの伯父夫婦が暮らすアパートで祖母の帰りを待つことに。昼日中なので伯父はおらず、アパートには伯母と智子の二人だけ。こんなところで祖母の帰りを待つくらいならば、一人で〝田舎〟の窓から空を見上げ、ボーっとしているほうがマシだった。
伯母も同じように思ったのでしょう、祖母が病院へ向かうと、伯母はすぐに買い物に出かけてしまいました。それもまだ一歳にもならない智子を置いて。それほど僕といっしょにいることを苦痛に感じるのでしょうね。
智子と二人きりになった僕。弟が生まれた時はうれしくてよく観察したのですが、智子に対しては生まれてくれてうれしいだなんて感情はまったくないし、もちろんかわいいとも思えない。なにせ伯父を僕から盗った憎い子供ですから。顔をチラッとだけ見て寝ていることを確認するとすぐにベビーベッドから離れ、窓から空を見ていた。
三〇分ほど経過しただろうか、物音も立てないように静かにしていたのですが、智子が目を覚まし泣き始めてしまった。母が弟の世話をしている場面をよく見ていたので、お腹が空いたのかおむつが濡れたかのどちらかだろうと思い、人差し指を智子の口に近付けてみた。智子は勢い良く指を吸い始めたので、台所でミルクを作って智子に与えてみた。もちろんミルクの作り方だって知っていて、母が作っていたいつもの手順どおりにしたので問題はないと思います。じっと僕の顔を見ながら一生懸命にミルクを飲む智子。
とりあえず泣き止んだ――。
そう思いながら哺乳瓶を持っているところへ伯母が帰ってきた。
「直樹、ベビーベッドに近付いて何してるの?」
「智子が泣きだしたから、ミルクをあげてた……
僕の返答を聞くと伯母はみるみる鬼の形相に変化していき、僕が与えていた哺乳瓶を僕の手から取り上げて放り投げ、ベビーベッドから慌てて智子を抱き上げた。
「ちょっとくらい泣いてても触らないで!」
伯母はそう言いながら僕を蹴り倒し、勢いよく頭から倒れてしまった。
「ごめんなさい……」
僕がしたことは蹴られるほど悪いことだと思って、頭を畳に擦りつけるようにして謝った。智子に近付くとこうなることを身をもって知ったし、智子が誕生してからは僕は歓迎されない人間だということを改めて知った。
智子に近付いたのは泣きだしたからどうにかしなきゃと思ったためで、泣かなければ近付かなかったし、蹴り倒されるほどに怒られることもなかった。本当に悪いのは泣いた智子だと真剣に思った僕は、智子への憎悪が一層高まった。
この夏はこの日以降ずっと〝田舎〟の部屋の窓から、青い空と山だけを見てすごした。朝から夕方までずっと、ただ外を見てすごした。