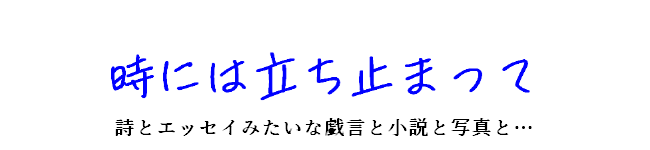妻には指一本触れない、妻もあきらめたようで僕には一切触れることはない、そんな夫婦だけど表面的には仲睦まじく映っているようで、ご近所からはそのように声をかけられることも多かった。実態は籍は入ったままだけど夫婦としては機能しておらず、ただの同居人だ。
そんな状態に我慢できなくなったのか、それとも目に映るモノすべてを自分のモノにしたくなるのか、妻は次々に服や靴、バッグに宝飾品そして腕時計などを買い漁るようになってきた。
基本的には僕は妻の行動に対しては何も言わない。お互いにするべきことをしておれば干渉しないと決めている。ただあまりにも買い物の金額や回数そして量が多く、家計をどのようにやりくりしているのか疑問に感じていました。
また仕事を終えて家に帰ると幼稚園から電話があり、降園時間をかなり過ぎても迎えに来られないので智大を園でお預かりしていると告げられ、慌てて幼稚園へ駆けつけ先生に平謝りして連れ帰ったことがある。その時間帯に妻は有名ブランドの展示会に参加していて、時間が過ぎていることに気付かなかったという。智大に聞くと、時々迎えに行くのが遅れることがあり、近くに住む保護者が智大をいっしょに連れ帰ることもあるという。
さすがにやるべきことをしていないから注意をするわけですが、たまたま忘れていただけだとか、私には私の用事があるといった逃げ口上に終始して、反省することなく再び同じことを繰り返すのです。
僕が何度も注意することに腹を立てたのか、智大を幼稚園へ連れて行かず百貨店や専門店での買い物に連れて行くこともあったし、一度は智大を家に置いて自分一人でお出かけしていたこともあった。今のところ幼稚園の送り迎えに支障が出ているものの、〝虐待〟などはないので胸を撫で下ろしていましたが、家庭内の亀裂の修復は不可能な状態になっていた。
このような状態の中、二〇〇〇年末に出した年賀状はさすがにゆっくりと一枚一枚に言葉を添える気力もなく、パソコンで宛名を印刷してそのままポストへ投かんした。
こんな手抜きの年賀状なんて出しても意味がないな――。
本当にそう思ったのですが、この流れ作業的に出した年賀状が功を奏したのか、二〇〇一年元日の夜に差出人がわからないメールが一通、携帯電話に届いた。
〝直くん、あけましておめでとう。元気にしてますか?〟
なんと差出人は智子だった。
〝智子、あけましておめでとう。僕のメルアド知ってた?〟
〝今実家に帰ってて、直くんの年賀状にメルアドが書いてあったから送ってみたの〟
〝いろいろとあって手抜きして年賀状を送ったから、メルアドを書いたものが届いたんだね〟
例年は数種類の年賀状を作って宛先によって使い分けていたのですが、今回は一種類しか作らず流れ作業的に全員に同じ物を送ったので、祖母宛の年賀状にもメルアドが記載されていたのです。本当に流れ作業的に送ってしまったので、すべての年賀状にメルアドを記載していたこともわかっておらず、智子からのメールでそのことに気付いたのでした。
〝何かあったの?〟
〝家のことだよ〟
〝奥さんのこと?〟
〝そうだよ〟
この後も夜遅くまで智子とメールのやり取りを楽しんだ。
智子は大学卒業後名古屋の企業で二年働いて退職し、今は大阪市内で販売員として働いているという。マンションをシェアして暮らしているらしく、僕はてっきり男と同棲をしているのかと思ったのですが、年上の女性との共同生活をしているという。
正月以降も毎日のように智子とのメールを楽しみ、ほぼメル友のような状態が続いた。でも僕は智子を誘うことはしなかった。会えば歯止めが利かなくなる気がするし、智子だって僕の家庭がどのような状況だろうと壊すきっかけになってはいけない、邪魔をしてはいけないという思いがあるから、あえて関西に住んでいることを僕には伝えてこなかったはずだから。
でも……、
〝直くん、私、本当は直くんに会いたい〟
〝僕だって本当は会いたい〟
〝会いたいよ、でも、会っても大丈夫かな〟
〝一度だけと約束して食事に行こう、一度だけ〟
〝直くん、誘ってくれてありがとう、本当にうれしい〟
こうして二月の中旬に智子と会う約束をした。
数分だけ待ち合わせの時間に遅れた僕。
「直くん!」
「智子、ごめん、待った?」
「少し早く着いたから……」
すっかり大人の女性になった智子は二五歳、お馬さんごっこして部屋の中を歩いたことや、お化け屋敷で抱っこしてお化けに近付けて泣かせてしまったことなど、遠い昔話のようだ。
そんな僕も今は三二歳、すっかりおじさんだ。智子が幼稚園や小学校に通っていたころはこんな子供なんてという思いが強く、七歳という歳の差は大きいと感じていた。今は智子がすっかり大人になったけど、僕がおじさん化しているから結局歳の差は縮まらない。
仕事終わりの智子はお腹が空いているだろうから、待ち合わせ場所からほど近い洋食店へ入って夕食を楽しんだ。
「こっちへ来ていたんだね。もう何年になるの?」
「えっと、一年と少しかな……」
「そっかあ、あのままずっと名古屋にいるのかと思ってたから、ちょっと意外だったよ」
「ごめんね、こっちへ来たことを教えなくて……」
「謝ることじゃないよ、智子は智子の人生を大切にすればいい、智子がこっちへ来たと知って、僕が邪魔するようなことになったらダメだし」
大学以降の智子のことをいろいろと聞いた。大学時代からスノーボードにはまって今でもよく滑りに行くこと。正直なところ大学時代は羽目を外しすぎたし、遊びすぎたこと。でもやりたいことを目いっぱい楽しめたから充実していたこと。いろいろな男性と付き合ったことも、同棲していたこともすべてを隠さず全部を話してくれた。
「いいなあ、それだけ充実して、楽しんで、たまには悩むこともあったとは思うけど、いい四年間をすごせたんじゃない?」
「うん!」
智子の話を聞いて自分では少し嫉妬するかなと思ったのですが、それどころかすごくうれしくなった。もしも関西の大学へ進み、関西でそのまま就職していたら、絶対に僕が智子の人生の邪魔になっていたはず。だから本当に良かったと思ったし、好きだからこそ智子の邪魔をしちゃいけないと思った。
もちろん僕の近況も隠さずにすべて話した。僕が選んだ妻の行いなんて、本当は恥ずかしくて隠しておくべきことだけど、すべてを話した。仕事のことや、僕は普段何をしてすごしているのかも含めてすべてを話した。智子にいろいろと聞いてもらいたくなったから。
店を出ると七時三〇分を回っていて、さすがに二月だからもう外は真っ暗だ。
「直くん、少し飲みに行く?」
「いや、やめておくよ。それより車で来ているから、ドライブにでも行かない?」
この時間だし流れ的に飲みに行くのはふつうかもしれないけど、車で来ているから飲みには行けない。いや、飲みに行かずにすむように車で来たのが本当だ。飲んで理性を失って、僕自身を止められなくなったら……。離婚して独り身ならば飲みに行くけど、どんな状態であれ僕は妻帯者だ。
車を西へと走らせ、海峡をつなぐ大きな橋のたもとにある海岸に車を止めた。外は雪は舞っていないがかなり風が強くて冷え込んでおり、車の中で智子と話をしていた。
「直くんって、今日待ち合わせした駅まで電車を運転しているんだよね?」
「そうだよ」
「私ね、時々あの駅のホームに立って、直くんに会えないかなって見ていたんだよ」
「本当に?」
「うん、名古屋へ行ってからも時々あの駅へ行っては、直くんを見つけられないかなと思ってホームで立っていたんだよ」
「全然知らなかった……」
「実家からの帰りにもよく探したし、大阪に来てからもよくあの駅のホームに立って、直くんを探してるの」
「見つからないだろ?」
「うん、一度も見つけられなかった……、よく見かけるおじさんは本当によく見るんだけど、直くんだけは見つけられなかった。私を避けているのかなって思ったりもしたよ」
「僕が智子を避けるはずがないよ……」
「何度かは香織も一緒にホームに立っていたことがあるだんだよ」
「香織はフランスから帰って来たの?」
「うん、今は東京に住んでいるよ。今もよく私の家に遊びに来るんだけど、二人でホームに立ってよく直くんを探したんだ」
「そうだったのか……、僕のことはすっかり忘れて、楽しくすごしているはずだと思ってた。とにかく、僕が智子の人生を邪魔していなくて良かったよ」
「直くんのことを忘れるはずがないよ……。いろんな人とお付き合いしたり、いろいろな遊びもしたけど、直くんのことは忘れたことがないもん、私……」
「智子……」
「直くんこそ、私のことを忘れていたでしょ?」
「忘れてないよ。もちろん四六時中智子のを事だけを考えているわけではないけど、ふと思い出すんだ、智子は今は楽しくやっているのかなって」
「ホントかな?」
「以前は忘れているというか、考えないようにしていたというか、智子のことを遠ざけていた感じ。遊ぶことや他の女性で心を上書きして、智子のことを見えないくしていたから」
「今は違うの?」
「うん、家のこともあるからかもしれないけど、智子のことを考える頻度が多くなってるよ」
「そっかあ、大変そうだもんね……」
「結婚することにした僕が悪いから仕方がない。でも僕が嫌いないい加減な生き方をされるのが許せなくてね。離婚するように持って行くしかないなとは思っているよ」
「うん……」
「離婚すれば独身に戻るけど、そんな僕はイヤだろ?」
「ううん……」
「離婚できたとしても傷モノだし、子持ちだし……、言ってみれば中古品だから……」
ちょっと車内の空気が重くなってきて、智子はそれを嫌ったのか、
「直くん、外に出よう」
「うん」
車から降りて冬の海岸を二人で歩いた。海から吹き付ける強い風は本当に冷たく、コートを着ていても震えが止まらない。
智子を見ると上着を車に置いてきて、タートルネックのセーター一枚で歩いている。
「直くん、寒いね……」
智子は僕の顔をじっと見る。
「うん」
僕は寒さではない別の震えが止まらない。
着ているコートで包むようにして、智子を抱き寄せようかな――。
何度も何度も同じことを考え、そのたびに腕が痙攣するんじゃないかと思うほど力が入ったけど、結局智子に触れることはできなかった。
「直くん、帰ろ……」
どのくらいの時間が経過したのかはわからないけど、とにかく智子はもうあきらめたようで車のほうへと歩き出した。そりゃあそうだよ、一度だけ会おうと約束して今日会っているのに、僕が何のアクションも起こさず無言でただ立っているだけだもん。
もしもすでに離婚していれば抱き寄せて、キスしていただろう。でも僕は妻帯者だ。実情は家庭の形をしていない仲の悪い同居人同士の関係だが、それでも結婚している事実がある。だから智子に触れることができなかった。
智子の家まで走らせる車の中では、智子はものすごく饒舌になっていた。僕に対する思いも吹っ切れたはず。それも仕方がない、智子がお膳立てまでしてくれたのに、僕は何の反応も示すこともできなかったから。
意気地なし。
いつまで経っても意気地なしな性分が直らない。大事な人を逃がしてもいまだに自分に対して言い訳をしてしまう。
この日以降、智子とのメールのやり取りはなくなった。僕みたいな情けない男が智子の行動に制限をかけてはいけないから。もちろん智子だって脈はないと思ったはずだし。
でもこの日以降も僕は智子のことを思い続けた。もちろん、あそこは抱き寄せるべきだったと反省の思いが多かったけど、姿は大人になっても、中身は昔と変わらない僕が大好きな智子のままだったから。
とにかくこれで智子と結ばれることはなくなったし、付き合ったり結婚することもなくなったはずだ。これからは『親戚』として『いとこ』として、そして世界中で一番智子を愛していると自負する男が、智子の幸せを願うだけだ。
智子を邪魔しないように、それだけだ。