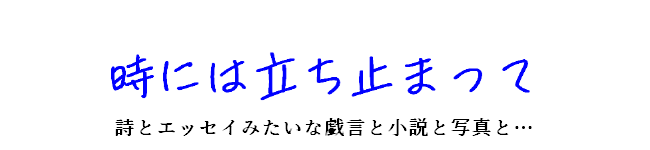智子は中部地方の大学に進んだのでさすがに会う機会を完全に失った。失ったのは会う機会だけではなく、智子という女性の存在が消えてしまった気になり、職場の仲間たちが頻繁にセッティングする合コンによく顔を出すようになった。彼女が欲しいといった思いはこれまでと同様にまったくなかったけど、自分にとって本当に大切だった女性を失った寂しさを紛らわす、ただそれだけのために合コンに顔を出していた。
何度目かの合コンで知り合った女性〝愛〟と惰性で付き合うようになり、子供を授かったので一九九四年末に結婚した。
新婚生活を味わう間もなく一九九五年一月には阪神淡路大震災が発生、僕も妻も家にも大きな被害はなかったけど、日々の生活や仕事は大打撃を被った。あの酷い状況下で身ごもった妻は生活できないだろうから実家に帰ってもらい、再び一人での生活が始まった。
元々時間がかなり不規則な仕事だったのに、勤めている会社の路線は寸断されてさらに不規則さが酷くなり、また交通網が寸断されて多くの社員の出退勤に支障をきたすことから、徒歩で出勤可能だった僕は連日早朝から深夜まで働き詰め。
おまけに会社の業績は震災での被害も重なり極度の不振に陥り、給料やボーナスが極端に減らされるなど、正直なところやる気なんて完全に消滅し、惰性で仕事をしている状態だった。
妻は実家近くの病院で六月に元気な男の子を出産し『智大』と名付けた。『智』の字は智子からもらったわけではなく、出生届に智大と記入する時にはじめて無意識のうちに『智』の字を選んでいる事に気付いたほどです。
七月に入って妻と智大が家に帰ってきて、三人での生活がようやく始まった。妻と子供にひもじい思いをさせてはいけないし、給料やボーナスも大幅に減額されているので僕は馬車馬のように働いた。所定の仕事のほかに朝の早出や夕方の残業を付加したり、休日も返上して出社する毎日。夜フラフラになって帰ってきて布団に潜り込み、目をつぶった瞬間に朝が訪れて布団から抜け出して出社、そこまでしないと満足なお給料がもらえない状態だったから。
八月になると、僕の子供を見てみたいと智子と香織が二人で我が家にやって来た。智子は大学二年生でもうすぐ二十歳、香織は高校三年生でもうすぐ一八歳になる。二人で関西で遊んだ後に伯母の親戚の家に泊まり、その家から我が家へやってきた。
「智大くんかあ、かわいい♪ 直くんによく似てるね」
今までに見たことがない笑顔の香織が、僕の子供を一生懸念にあやしている。
それに対して智子は僕の子供を見てかわいいとは言うものの、それほどうれしそうにはしていない。どちらかと言えばあまり興味がなさそうに見える。それ以上に気になったのは、智子はやたらと妻を観察しているように思えたこと。妻のことが気に入らないのか、香織とは逆にこれまでに見たことがない険しい表情をしている。
僕がベビーバスで智大を|沐浴《もくよく》させたのですが、その様子を満面の笑みで見る香織と、どこか白けたような顔をしている智子。智子の表情を見ていると僕も笑ってはいけないという気持ちになってしまうし、どうしても気になって智子にばかり視線を送ってしまう。
智子はどうしたんだろう、僕が機嫌を悪くさせてしまったのかな――。
妻が入浴している時に智子が、
「直くん、赤ちゃんができたから結婚したの?」
「お姉ちゃん、それは聞いちゃダメよ。実際にそうだとしても、今は幸せな家庭を築いているんだもん」
香織が珍しく火消しの言葉を発した。
「たしかに、授からなければ結婚はしなかっただろうね」
「直くん、ごめんね、ちょっと気になって聞いちゃった……」
〝子供ができたから仕方がなく、好きでもない相手と僕が結婚した〟
そのことが智子には不服なようだ。
その後はお風呂から上がった妻も交えて四人で静かに世間話をしたのだが、その夜のこと。
「ねえ、あなた、そっちへ行ってもいい?」
狭い団地の寝室で布団を並べて寝ている僕たち夫婦。
「隣の部屋では年ごろの『いとこ』たちが寝ているんだぞ。丸聞こえになるぞ」
「いいの、聞かしてやりたいぐらいだもん……」
「それは絶対にダメ! ちょっと非常識すぎるよ」
それでも妻は素っ裸になって僕の布団に潜り込み、僕のパジャマのズボンに手をかけたけど、
「今晩は絶対にダメだ、いい加減にしてくれ!」
妻はむくれて自分の布団へ戻って行った。
小声でのやり取りだったけど、ふすま一枚を隔てた隣の部屋にも聞こえていたはずだ。お客が、それも年ごろの親戚たちが来ているのに求めてくるなんて一体どんな神経をしているのかな、そして妻は何を考えているのかな。僕には到底理解できない。
〝直くん、赤ちゃんができたから結婚したの?〟
智子のこの言葉を思い出し、布団に潜り込んで心の中で答えた。
〝そう、好きでもないのに関係を持って子供ができたからだよ〟
智子はこういう答えを待っていたのかな。それとも、
〝授かり婚だけど好きだったから結婚したんだ〟
そんな言葉を待っていたのかな。
僕は結婚し子供もいる身。だけど智子を見ると、心の奥底に沈んでいた本当の気持ちが浮かび上がってくる。そして今の生活に対する絶望感に|苛《さいな》まれる。
僕が愛に手を出したから。
僕が智子に告白しなかったから。
すべては僕が悪い。
選ぶべきことを拒否し、選ぶべきではないことばかりに手を出したから。
そうだよ、悪いのはすべて僕なんだ。
布団の中でこんなことを考えていると、自然に涙が頬を伝った。
翌朝はちょっと微妙な空気が流れる中、四人で食卓を囲んだ。だれも口を開かない沈黙の食卓は、やっぱり智子も香織も妻の言葉を聞いていたことを証明するものです。
朝食を食べた後すぐに広島の実家への帰り支度をする二人。支度が終わると僕は新幹線の駅まで電車で二人を送り届けた。三人で横並びに座る電車の中で香織が話しかけてきた。
「直くん、直くんの奥さんってちょっと変だね?」
「昨夜聞こえただろ? 変な会話を聞かせてごめんね」
「さすがにお姉ちゃんと二人で引いちゃったよ……」
香織は昨夜のことを話してくるが、智子は黙ったままだ。
「直くん、結婚して幸せ?」
「うん……、と言うべきかもしれないけど、流れに身を任せているだけかな」
「智大くんができなかったら、結婚していない?」
「していないね。結婚なんて全然考えていなかったもん」
「やっぱりお付き合いする相手は考えなきゃいけないなあ……」
「香織はピアノを続けるの?」
「うん、昨夜は話さなかったけど、フランスへピアノ留学するの」
「え? 本当に? 一人で行っちゃうのか……」
「うん、だから日本を離れる前に直くんに会っておきたかったから」
「すごいなあ、一人でフランスへ。僕にはそんな勇気がないから尊敬しちゃうよ。でも僕に会いにって、香織は小さなころから僕のことをあまり良く思ってなかったよね?」
「そんなことはないよ、口の悪さはお母さんと同じレベルだと思うけど、でも、直くんが来るってわかると本当に楽しみにしていたんだもん」
「本当かよ……」
「本当だよ、私はずっと、かっこいい『いとこ』のお兄ちゃんって思ってるもん」
智子はまだ黙っている。先に子供ができ、あんな妻と結婚した僕のことを見損なったのか、それとも軽蔑しているのかな。智子は昨日家に来た時からあまり話さないし、妻を観察するように見ていたし、智大を見る目も歓迎しているようには見えなかった。相手がだれであれ結婚したこと自体をよく思っていないのかな。
「智子、がっかりした?」
「うん……」
「相手があの妻だから? それとも結婚したこと自体にがっかりした?」
「両方……」
「そんな顔してたよな」
「お姉ちゃん、直くんに会えるって楽しみにしていたのに、奥さんと智大くんを見たら急に険しい顔になるんだもん。でもお姉ちゃんっていつもは無理してでもニコニコするのに、珍しく抑えきれなかったね」
「うん、直くんの智大くんを見る目を見ると何だかね……、盗られたって思って……」
智子が生まれた時、僕をかわいがってくれていた智子の父である伯父を盗られた気がして、僕は智子のことが大嫌いだった。そして智子ばかりを見るようになった伯父も大嫌いになった。智子も同じような感情に見舞われたのかな。
「智子、僕も昔に同じようなことを思ったよ」
「直くん、前に言ってたよね」
「お姉ちゃん、直くん、何の話?」
それで僕が簡単に説明すると、
「それって大好きな人を盗られたっていう感情だよね、お姉ちゃんは本当に直くんのことが大好きだから同じように思ったってわけか……」
「直くんのことが大好きって……」
「お姉ちゃん、本当に直くんのことが大好きだったでしょ? 私は理想の親戚のお兄ちゃんとして直くんのことが好きだけど、お姉ちゃんはずっと直くんと結婚したいって言ってたもん」
「それはお父さんがずっと、智子は直樹に結婚してもらえって言ってたから……」
智子は下を向いてしまった。
「智子のお父さんはそんなこと言ってたの?」
「お父さんはつい最近までずっと言ってたよ」
「それって女の子しかいなくて、男の子が欲しかったからかな?」
「お姉ちゃんには直樹に結婚してもらえ、私には徹に結婚してもらえって。徹くんは面白くないからイヤってずっと言ってたけどね」
「弟は僕とは違って、能書きばかり垂れるから面白味には欠けるかな……」
「直くんもそう思う? 徹くんはいつも兄貴よりここがスゴイぞって自慢ばかりするんだもん。直くんの弟とは思えないし、あんな人とは結婚なんて絶対に無理だわ」
智子は顔を赤くしたまま黙っていた。
新大阪駅の新幹線乗換口の前でお別れのあいさつ。
「せっかく来てくれたのに、あまりいい感情を持たずに帰らせちゃうね、ごめんね」
「直くんは謝らなくてもいいよ、かわいい智大くんにも会えたし、これで思い残すことなくフランスへ旅立てます」
「そうだね、香織はフランスに行っちゃうからしばらく会うことはないね。とにかく体に気をつけてすごしてね」
「フランスに行ってから、直くんに手紙を書いてもいい? 奥さん怒っちゃうかな……」
「それは気にしなくても大丈夫さ、手紙、待ってるよ」
「ありがとう、直くん」
「智子も本当にごめんね、不快な思いをさせちゃって……」
「うん……」
香織が先に自動改札を通り笑顔で僕に手を振ってきた。智子は自動改札を通る前に、
「直くんは昔のままなんだよね……」
「昔のまま?」
「うん。直くん、本当に好きな女性って……」
「ああ、妻ではない。ずっと同じ女性が好きだよ、これからもずっと……」
「私もずっと同じ人が好き、これからもずっと……」
智子は目に涙を潤ませながら、軽く手を振って自動改札を通って行った。
智子も香織も何度も振り返りながら手を振ってきて、二人がエスカレーターに乗って見えなくなるまで僕も手を振った。僕は涙を溜めることができなくなり、ぽろぽろと床に落した。
今日も告白はできなかった。だって僕は結婚して子供がいるのに告白なんてしちゃいけない。でも本当に僕が好きな女性は智子だと再確認できた。これで十分だよ。勇気を出してもっと昔に智子に告白しなかった僕が悪いんだよ。
感傷に浸りながら電車に揺られて家に帰ると、玄関先で妻が僕に口論を仕掛けてくる。
「何、あのいとこたち! 特にお姉ちゃんのほう、まるで品定めでもする姑のように私をじろじろ見まわして、何様のつもりなの! 本当に感じが悪い!」
「そう怒ることはないだろう! 僕が選んだお嫁さんはどんな人なのかなと、興味を持って見ていただけじゃないのか?」
「あの女の目は絶対に違う! 私のことを泥棒のように見ていたわよ。まるで私があなたを盗んだ、そんな目だったわよ!」
「あのなあ、親戚だぞ、僕のいとこだぞ、血の繋がりがあるんだぞ! 何を意味不明なことを言って怒っているんだ! いい加減にしてくれ!」
「あの女の目は私を憎んでいる目よ! あなたを奪ったことに反発する憎しみの目よ! 智大を見る目だって、なぜ私に生ませてくれないのという抗議の目よ!」
「何を言ってるんだ? なぜ僕のいとこがそんな感情を持つんだよ。ただ漠然といとこのお兄ちゃんの結婚相手として見ているだけだろ? それ以上何を思うというんだ?」
「違う! あのお姉ちゃんのほうは女の顔をしてあなたとしたがってる、そんな目をしていたのよ! やっぱり昨夜は無理にでもあなたとするべきだったわ。あなたとしているところを聞かせ、いえ、ふすまを開けて一つになっているところを見せつければ良かったのよ。もう何を思ってもあなたは手が出せない、それをはっきりと認識させるべきだった」
「君はそんな理由で昨夜求めてきたのか?」
「そうよ、〝ご親戚〟たちに私のモノだとわからせるためよ。憧れの人が私と一つになっている場面に遭遇すれば、もう落胆して絶対に手を伸ばしてくることはないでしょ?」
「昨夜しなくても、智大がいることでそのくらいわかってるだろ!」
「違う、しているその場面に居合わせる事で、はっきりと認識させられるでしょ」
「信じられないよ……。本当に人として信じられない……」
「いいわよ、信じられなくても。妻の地位にいるのは私だと示したかっただけなのに。その証拠をあの女に示すことのどこがおかしいの?」
「君は道具や手段としてするわけ? あり得ないよ……」
「でも離婚はしないからね! あなたと別れれば、あの女があなたの妻の地位をすぐに奪いに来る。そんなことは絶対に許さないから! あなたとあの女が一つになるだなんて、絶対に許さない! あなたに触れていいのは妻の私だけ、あの女があなたに触れられないように、妻の座は絶対に渡さない!」
「あのなあ、結婚するにしても僕の意思が必要なんだよ。僕は『いとこ』と結婚する気なんてないよ」
「あなたになくても、あの女が迫ってきたらあなたは絶対に抱くわ。あなたはそういう男だもん。そしてあの女と結婚するのよ!」
「勝手に言っておけばいいだろ! バカらしくて話をする気にもならないよ」
「あなたはそうやって誤魔化そうとしているだけ、あなただってあの女を抱きたい、自分のモノにしたいと思っているじゃない。あなたを見ているとそのくらいわかるのよ」
「はいはい、そうですか。勝手に何でも想像しておけばいいだろ!」
智子のことが好きなのは事実だけど、智子を抱きたいだなんて考えに至ったことはこれまで一度もないし、結婚やお付き合いどころか、女性として『好き』と伝えることだってできていないのに。僕は手が早いかもしれないけど、智子に対してはかなり臆病なんだよ。
この日以降も妻は頻繁に求めてきましたが、僕は妻を抱くどころか指一本触れることもありませんでした。女性として、人として見ることができなくなったから。