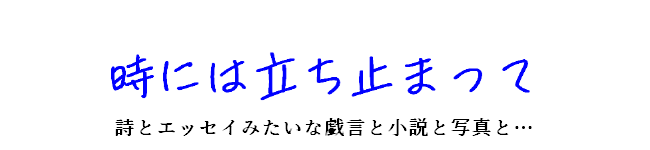「智子の旦那さんは年下で、雰囲気が直樹にそっくりだと兄ちゃんが言っていたわよ」
智子の披露宴の招待状を受け取った母は、伯父に電話してお祝いの言葉を贈ったらしく、その時に旦那になる人のことをいろいろと聞いて僕に電話してきました。
「僕にそっくり? 雰囲気が?」
「うん、兄ちゃんが言うには直樹の小さな時と瓜二つって言ってるわ」
「僕が小さな時? どんな大人なんだ?」
「幸子(伯母)さんも同じように言っているわよ。はじめて家に連れて来た時は驚くくらい直樹に似ていて、顔から話し方から、座ったり歩いている姿までそっくりだって」
「伯母さんは僕のことが嫌いなのに、そんな人との結婚をよく許したね」
「智子や香織より年下だからよ。子供が姉妹二人だけでどうしても跡取りの男の子が欲しかったでしょ、幸子さんも兄ちゃんも。そこへ香織よりも年下の彼氏を智子が連れてきたから、かわいくて仕方がないらしいのよ」
「ふーん、そんなものなのかなあ……」
「そうそう、徹は赴任先から呼び戻さなくてもいいわよね」
「一応連絡は入れておくよ、『いとこ』の結婚式だけのために、ただでさえ忙しい仕事を休ませてニューヨークから帰らせるのも酷だと思うから」
「それとね、お祖母ちゃんは式には出ないらしいわよ」
「こっちへ来ないの?」
「車にずっと座って移動するのも大変だし、智子の旦那さんには何度か会っているしね」
「そっか、広島の伯父の家には何度か連れて行ったんだね」
僕に雰囲気が似ていて、智子より年下の旦那――。
たまたま結婚しても良いと思った男性が僕に似ていたのかな。まさか僕に似た男性を探すことは考えられないし。もしも僕が智子の立場だったら、絶対に僕に似た人を探しもしないし、好きにもならないと思うけどな。僕が今から結婚を前提とした交際相手を探すときには、智子に似た女性は除外すると思うんだ。だって似ていたらずっと智子を引きずり、ついつい本物の智子と比較してしまうから。智子は僕の中では他の女性とは違う場所に君臨していて、だれも近付けないほど僕にとっては大切な女性。だから、智子に似ている女性なんて僕の中ではあり得ないし、もしもいたとしても好きにはなれない。僕の中では智子は特別な存在だから。
だとしたら智子にとって僕は好きな〝タイプ〟だったということかな。僕〝みたいな〟男性が好みだから、同じような〝タイプ〟で僕〝みたいな〟男性を選んだ。それならば僕も合点がいくし、智子の僕に対する思いもよくわかる。
なるほど、結局は僕と智子は相思相愛だったとしても、かなりの温度差があったということだ。そうだとすれば、僕にはもう手が届かない智子なんてきれいさっぱり忘れて、子持ちでも良いという女性を探そうかな。これは智子にとっても新しい門出を迎えるとともに、僕にとっても新しい道を歩むためのきっかけになるかもしれない。
とは言っても、僕はやっぱり智子のことが好きだ。とにかく智子の邪魔にならないように生きていこう、それが僕にとって正しい道の選択だと思うから。
梅雨真っただ中のこの時期らしいどんよりとした雲に覆われた大安吉日の今日、大阪の某高級ホテルに入って行った。招待状に書かれた親族が集まる部屋に入ると、涙目の伯父とにこやかな伯母の姿があった。
伯父を見ていると、結婚して初めての子供が授かれば、僕をかわいがるどころではなく智子を溺愛するよなと思った。智子のせいで伯父を盗られたと小さなころは思っていたけどそうではなく、自分の子供でもない甥を異常なほど溺愛する変な思考から、実の娘をかわいがる正常な思考に戻っただけのことなんだよね。
伯母の今日のにこやかな顔はおそらく始めた見たと思う。この人って智子はどうでもよく、香織のことだけを考えていると思っていた。でも今日のような日にその姿を見ると、やっぱり智子の母親なんだな。あの笑顔がそれを物語っている。
「直くん、お姉ちゃんの旦那さんを見てビックリしちゃダメだよ。本当に直くんにそっくりなんだから。私はよく三人で遊びに行って、名前は健一って言うからけんちゃんって呼んでいるけど、どこからどう見てもけんちゃんと直くんそっくりなんだから」
「その話を僕も聞いたけど、そんなに僕に似ているの?」
「今日の結婚式も、けんちゃんの代わりにお姉ちゃんの隣に直くんがいても全然違和感はないと思うよ」
「さすがにそれはないだろう、新郎は香織よりも年下なんだろ? 僕は智子より五歳以上年上なんだし、僕が智子の横にいたら〝何? あのおじさん〟ってザワザワするよ」
「年齢は仕方がないけど、でも本当にビックリするくらい似ているから楽しみにしていてね」
「そうなのか……、智子がどんな人を選んだのかじっくり観察するよ」
そこまで話をすると、
「ちょっと、直くんこっちに来て……」
香織がだれもいない部屋の隅へと僕を引っ張った。
「お姉ちゃん、昨日からずっと泣いているんだよ、さっきもちょっと見に行ったら目に涙を溜めていて……」
「結婚できるのがうれしいんだろ? イイことじゃないか」
「違うよ、お姉ちゃん、今になって直くんのことを考えているみたいなの」
「僕のこと?」
「うん、前にも直くんに言ったけど、お姉ちゃんね、本気で直くんと結婚したかったんだよ。本当に小さなころからずっと。けんちゃんと結婚したくなくなったとかじゃないけど、これまでのいろいろなことを思い出していると、自然に涙が出てくるんだよ」
そう言われても、智子は他の人の奥さんになるのに僕にはどうしようもできないよ。もちろん僕だって智子のことが今でも大好きで、何の支障もなければ結婚したいくらいだけど、今日は智子が選んだ人と結婚することを皆に披露する場。まさか花嫁を連れてこの場から逃げ出す映画のワンシーンみたいなことはできるはずもないし、もうどうにもできないよ。
結局は重大な節目で自分の本当の意思とは逆ばかりを選び、それがすべて裏目に出たから今日のこの日を迎えたんだ。もっと早く離婚していたら今日の状況にはならなかったかもしれないし、前妻と関係を持たなければ今の状況にはならなかったかもしれない。智子と一度きりの食事に行った時に抱き寄せていたら状況は違ったかもしれない。とにかく節目での智子に対する僕の選択がすべて裏目だったから今日の日を迎えたんだ。今日智子を泣かせたり涙目にしたのも僕の責任。でも僕が取れる責任って今は智子を祝福してあげることだけ。それ以外には何もできない。
僕だって智子のことが大好きだし、ずっといっしょにいたいと今でも思っているけど――。
この親族が集まる部屋には新郎側の親族もいます。それもうまい具合に部屋の真ん中あたりを境界線にして、片側が新婦の親族、もう片側が新郎の親族という感じに。
その部屋へ披露宴の司会者らしき人が入ってきて定型のあいさつをしたあと、相手方の親族へ簡単なあいさつをするようにと促してきた。
新郎の親族が一人ずつ境界線あたり進んできては簡単なあいさつを行い、続いて智子側の親族が同じように境界線辺りへ進んではあいさつをしていく。
「初めまして、新婦の智子のいとこにあたります、岩舟直樹と申します」
それだけ言って頭をペコリと下げたのですが、新郎側の親族がザワザワし始める。何か変なあいさつをしちゃったのかなと思いながら、新婦の親族たちの最後部へ隠れるように移動した。
「ね、直くん、みんなけんちゃんに似ていると思ってザワザワしたでしょ」
香織が僕の耳元でささやいた。
新郎新婦が入場して披露宴が始まった。新郎を見た瞬間に母が、
「本当に直樹にそっくりよ、良く似ているわ」
僕も新郎を凝視したのですが、どこが似ているのかがわからない。顔は僕よりイイ男だし、歩く姿も僕とは違って何だか格好良く見えるし、僕と似ているところを探すのが大変だと思ったけど、親族たちは一様に僕によく似ているとひそひそと話をしている。
「パパ、あの人パパに似ているね」
息子にまで言われる始末。僕の周りの人から僕はああいう感じに見られているのか、よく言えばやさしそうだけど、言い方を変えれば決断する力が弱くて尻に敷かれる感じ。
たしかに似ているのかもしれない――。
会社の同僚の披露宴にはこれまでにも数多く呼ばれてきて、もう二時間以上が経過してお開きの時間になったのかと思うことが多かったけど、今日の披露宴はなぜか頭が空っぽになっているというか、椅子に座っていても体がフワフワと浮いているように感じる。お料理もかなり高級なものが用意されていたけど、口に入れてもまったく味を感じない。かなり高級なワインをいただいたけど味もしないし酔いもしない。思考が完全に停止しているようです。
テーブルラウンドでキャンドルサービスを行っていましたが、いつもならばシャッターチャンスだとばかりに写真を撮りまくるのに、今日はカメラを持ってくることを忘れていた。忘れたというよりは頭にまったくなかった。
よくいたずらしてキャンドルを少し水で濡らしたりもするけど、今日はそんなことも頭に浮かばなかった。僕のいるテーブルのキャンドルに二人で火を灯すとき、なぜか視線をよその場所に移してまったく見ていなかった。やっぱり新郎への嫉妬かな、それとも智子のウエディングドレス姿をまじまじと見たくはなかったのかな。自分で意識して目を逸らしたわけではないけど、なぜかその瞬間は見ていなかったし〝おめでとう〟の言葉もかけられなかった。笑顔の智子が他のテーブルのキャンドルに火を灯す場面はしっかりと目で追っていたのに。
「直くん……」
智子は僕が座る席から別のテーブルへと移る時、たしかに僕の名を耳のそばで呼んでいた。気のせいかもしれないけど、僕の耳にははっきりと智子の声が入ってきた。
友人の祝辞は当然だけど新郎新婦を持ち上げる内容で、いつもはあまり真剣に聞くことはないのですが、今日は智子の今の姿が話されるんじゃないかと聴き入りました。簡単だったけど新郎との出会いについても語られていたので、そうだったのかと思うところも多かった。その話からは、僕と一度きりの食事のあとにスノーボードで訪れたゲレンデで出会ったようです。
そっかあ、あの時に抱き寄せもしなかったから愛想を尽かされたんだ――。
今さらながら、再び自分自身の選択ミスを嘆くしかなかった。
「お父さん、お母さん、二六年間育ててくれてありがとうございました……」
新婦智子から伯父と伯母への感謝の手紙です。『いとこ』とは言え離れて暮らし、会うのは数年に一度だったから僕が知らないエピソードも多く、智子って本当に大切に育てられていたなと、少し感激しながら聞いていました。でも何だかおかしい、たいていの新婦さんは手紙を半分も読んだあたりで泣いて、その様子を見て披露宴会場にいるみんなももらい泣きするのが定番。でも意外と智子は淡々と読み上げていきます。それが悪いわけではないし、緊張して泣くどころじゃないのかもしれない、でも、
「親戚のお兄ちゃんには本当にかわいがってもらい、感謝するとともに私の大切な大切な思い出です……」
この一文を読み上げると智子は感情が爆発し、大粒の涙を落とし始めた。
「直樹、智子が今読んだ部分って直樹のことじゃない?」
母が僕にぼそっと話しかけてきました。
「伯母さんのほうの親戚の話じゃないの? 向こうの親戚たちとはよく行き来していたはずだし、僕は数年に一度しか顔を合せることもなかったから僕のことじゃないよ」
一応は否定して伯母の親戚の話だととぼけましたが、もちろん僕のことだとすぐにわかったし、ドキッとしました。
披露宴の、それも父母への感謝の手紙に僕のことなんて入れなくてもいいのに――。
披露宴が終わり会場から退席すると、新郎新婦とそれぞれのご両親が出席者へのあいさつのために立っている。伯父と伯母に一言だけ祝意を伝え、隣に立つ新郎新婦にはじめて〝おめでとう〟と声をかけた。
「直樹さんですか? 智子からいろいろと話は聞いております」
新郎が僕に声をかけてきた。
「お幸せにね」
僕はその一言だけをかけた。
智子は僕と視線を合わさなかったし、話してくることもなかった。新郎の両親の前に立った時に智子は僕のほうを向いていたが、その目には涙が溜まっているように見えた。
「あの、すみません、よろしければ二次会へ来てもらえませんか? 智子が来てもらいたいと言っているのですが」
「子連れなのでご遠慮させていただきます、ごめんなさい」
あいさつを終えるとすぐに智子の友人らしき女性に声をかけられたがお断りした。参加しても良いのですが、今日の僕は智子の幸せそうな顔を見ると泣いてしまう。悲しいとか嫉妬ではなく、智子との数々の思い出が頭の中によみがえってきて自然に涙を落とすと思うから。それに子供の前で父親が泣く姿を見せたくはないですし。
「直くん!」
「香織は二次会へ行くの?」
「うん、直くんは?」
「智大がいるから帰るよ」
「直くん、本当は直くんに祝辞を読んでもらうつもりだったんだよ」
「僕に?」
「うん、お父さんもお母さんもそのつもりだったけど、お姉ちゃんがいやがったんだよ」
「そうなんだ……」
「だって絶対にお姉ちゃんとの大切な思い出の話をするでしょ」
「僕の智子との思い出が、智子にとってどうなのかはわからないけど……」
「お姉ちゃんね、直くんの祝辞を聞いたら号泣するからいやだって言ってたよ」
「それより、お父さんとお母さんへの感謝の手紙、あれって……」
「あれは私も知らなかったから驚いたけど、絶対に直くんのことだよ」
「香織のお母さんの親戚の話とかじゃないの?」
「それは絶対にないよ。だっておじさんやおばさんばかりで、私もお姉ちゃんも話しはするけど別にって感じだもん」
「そうなの? 小さなころはよく向こうの親戚の家に行ってなかった?」
「行ってたけど、あれは連れて行かれていただけだもん」
「そうなの?」
「うん。でも自分で読んで直くんとのことを思い浮かべて号泣しちゃうって、やっぱり直くんのことが忘れらないのよ、お姉ちゃんは……」
智大と二人で電車に乗って家に帰る時、
「パパ、泣いているの?」
「目にゴミが入って痛いんだよ」
「大丈夫?」
「うん、明日には元気になってるよ」
結局は子供の前で父親が泣く姿を見せてしまった。