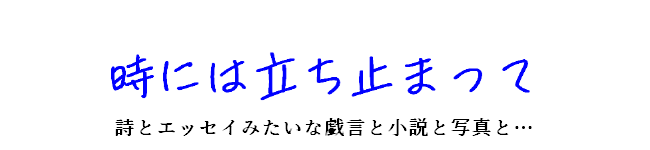僕は大学へは行かずに就職を選んだ。勉強が好きではないし、大学へ行って何かを学びたいという意欲はゼロだったから。ただ同級生たちからは、
「大学なんて遊ぶのが目的で行くだけで、勉強なんて片手間だよ」
「真剣に学ぶために大学へ行く奴なんてごく一部だよ。みんなが行くから俺も行くだけさ」
「高校出ていきなり働くのも大変だろ? バイトじゃないんだしさ。大学へ行ってゆっくりと将来の身の振り方を考えればいいんだよ」
「お前、それだけ頭がいいのに大学へ行かないのはもったいないぞ」
僕が通っていた高校は公立の進学校で、卒業生の七〇パーセントくらいは大学へ、二九パーセントくらいが専門学校へ、残りの一パーセントくらいが就職するような学校です。同級生で就職を選んだのは僕を含めて四名しかいません。
僕は遊ぶために大学へ行くという考えには行き着かないし、何から何までみんなと同じ行動というのも好きではない。高校の成績が良いのに大学へ行かないのはもったいないという考えも理解できないし、そもそも何かを学びたいというつもりがないから、大学へ行って無駄な四年間をすごすというのも僕は好きではない。何かを見つける目的で大学へ行くのはまだわかるけど。
僕の父や母そして伯父だって中学校を卒業して働き、一人前に社会生活を送れているわけだから、大学へ行かずに働くという選択肢が悪いとも思えないし。
ただ就職先を選ぶのは慎重に、とにかく安定していて一生働くことができる企業を選ぼうと思った。進路指導の先生方が高卒でも十分活躍できる企業としていくつかピックアップし、その中から地元の鉄道会社を選んだ。
僕は小さなころは電車に乗るのは好きだったけど、今は鉄道にはまったく興味はない。ただ僕を連れて家の前で国鉄を眺めながら列車の名前を教えてくれたりしていたから、父は鉄道に興味があったのはたしかだと思う。僕には父と同じ血も流れているから、それで鉄道会社を選んだのかもしれない。
一九八七年に就職してすぐに一人暮らしをはじめ、二年間の駅員生活を経験した後に試験に合格し、一九八九年からは車掌をしていた。駅員の時は休暇を思うように取ることができず、車掌になった一年目の夏はとんでもない残業と休日出勤に追われた。
駅員時代には念願だった中型限定ではあるけど二輪免許(現在の普通二輪)を取り、車掌になってからカワサキのゼファーを購入した。職場の運転士や車掌の人たちとツーリングに出かけることがかなり多くなり、このころの僕の頭の中からは広島の伯父の家ことは完全に消失していた。当時付き合っていた彼女もいたが、それ以上に職場の人たちと遊んでいるのが楽しかった。
車掌二年目の一九九〇年の夏にまとめて休暇を取ることができ、三泊四日で職場の人たちと四国一周のツーリングに出かけることになったのですが、最終日は一部区間が開通していた西瀬戸自動車道(しまなみ海道)とフェリーを使って本州側へ渡ることになっていたので、尾道でみんなと別れて伯父の家へ行くことにしました。伯父の家へ行くのは高校二年生だった一九八五年以来、五年ぶりです。今回も二泊の予定ですが、また切り上げて早く帰るかもしれません。
伯父の家に着くと祖母と伯母、『いとこ』の香織の三人がいた。
「直樹もすっかりオッサンになったなあ、お父さんが小さいころによくかわいがっていたけど、今じゃその面影もない」
いきなり伯母の毒舌を見舞われたが、今の僕は仕事で毎日のように、伯母なんて足元にも及ばないもっと強烈な人格の客を相手しているから、この程度の言葉ではなんとも思わない。昔の僕は当然ながらただ腹を立てていたけど、今は冷静にそういう人だからとしか思わない。
香織は中学一年になり随分雰囲気が変わった。以前会った時は小生意気で伯母をコピーしたような子供だったけど、少し棘の先端が丸くなったのか物腰が柔らかくなった気がする。
「直くん、オートバイに乗るんだね。そんなイメージがなかったから驚いたよ。また機会があったら後ろに乗せてね」
「香織、あなたにはピアノがあるんだから、下手な運転で事故にでも巻き込まれたらピアノなんて弾けなくなるわよ」
伯母の毒舌は相変わらずだが、なるほど、僕がオートバイに乗ってきたことが気に入らないみたいだね。大事な大事な娘が変なことに感化させれてピアノが弾けなくなったら大変、そんな気持ちからの言葉だろう。
伯母と香織にお土産を手渡して祖母の部屋へ行き、二時間ほど話をした。
「直くん!」
夕方五時過ぎ、客間でくつろいでいると智子が入ってきて、僕の名前を呼んですぐに出て行った。智子のセーラー服姿を初めて見たけど、あの小さかった子供がねえ……、という感想しかない。中学三年生の夏休みなので部活は引退しているが、登校日で学校へ行ったあとそのまま後輩たちの練習に混ざっていたらしい。
着替えた智子が再び客間へやってきて、
「直くん、今度はいつまでいるの?」
「とりあえず今日は泊まっていくけど、後どうするのかは決めていないよ」
「家の前に止めているバイクって、直くんの?」
「うん、そうだよ」
「直くんがオートバイって、ちょっと意外だな」
「香織にも言われたよ」
「後ろって乗れるのかな?」
「乗れるよ、香織に後ろに乗せてくれって言われたよ」
「香織を乗せるの?」
「何も約束はしていないよ。でも香織はお母さんに危ないから乗るなって言われてた」
「危ないのかな……」
「まあ、危なくないとは言えないけど……、車だって事故に巻き込まれることはあるし……」
「ねえ、直くん、明日は一日家にいるから……、あの……、勉強教えて」
「僕より智子のほうが賢そうに思えるけど……、わかる範囲でね」
「明日はお昼からお母さんと香織はピアノの講師の家に行くはずだから……」
「香織はいないのか……、じゃあ、お馬さんごっこ……、もうそんな歳じゃないか」
「ううん、直くんと約束したもん、お馬さんごっこしてくれるって!」
「いいけど、恥ずかしくない?」
「うん……、でも、約束だもん!」
翌日は朝から客間へ教科書や参考書を持ってきたので、僕もいっしょに勉強していた。高校を卒業して四年が経過すると、高校時代に必死になって覚えたことがかなり抜け落ちている。どうやら僕の脳は網目状になっているのか、覚えたことをとどまらせることはできないらしい。
お昼過ぎには伯母と香織はピアノ講師の家に出かけ、僕は客間で寝転んでいた。
「直くん、香織が行ったから、お馬さんごっこして……」
「本当にするの?」
「だって、直くんと約束したもん」
僕は起き上がって四つん這いになり、智子は僕の腰のあたりに乗ってきた。
「やっぱり重くなってるなあ」
「重かった? 降りようか?」
「そうじゃなくて、前にお馬さんごっこした時とは違って、大きくなったなと思ってね」
「あの時は幼稚園の年長組だったから」
「今は中三だもんなあ、そりゃあ大きくなるよな」
「直くん、やっぱりやさしいね」
「やさしいかな……」
智子を腰に乗せて部屋の中を三周ほどしてお馬さんごっこは終わり、少し疲れたので一階へ降りてコーラを飲んでいた。
「直くん、もう疲れた?」
「少しだけね、でも大丈夫だよ」
「あのね……、オートバイに乗せてほしい……」
「いいよ、近所を少し走ろうか?」
「うん!」
「智子、ヘルメットはあるの?」
「自転車に乗る時のヘルメットがあるよ」
「まあ、それでいいか。長ズボンに履き替えておいで、できれば上も長袖のほうがいいけど」
「どうして?」
「走っているとほかの車がはねた小石が飛んできたり、虫がぶつかってきたりするからね」
「ふーん、じゃあ着替えてくる」
智子は長袖のTシャツとジーンズに履き替えてきた。
「じゃあ、行こうか」
できるだけ交通量の少ない道を選んでノンビリとバイクを走らせた。
「智子、僕の腰に手を回してしっかり持っていないと危ないよ」
智子は左手で僕の服をつかみ、右手はシートのベルトをつかんでいるようだったので声をかけた。
「えっ? あ……、うん……」
「そして、体を僕にくっつけるようにして乗るんだよ」
中学三年生の女の子が男の腰に手を回し、体をくっつけることは勇気がいるかもしれないけど、離れていると危ないし僕も運転しにくいですから。
三〇分ほど走り町はずれの小さな何もない空地の前にオートバイを止め、道端の縁石に二人で腰かけた。
「昨日祖母ちゃんに聞いたけど、智子は高校卒業後に働くつもりなの?」
「うん、直くんみたいに大学へ行かずに働こうかなって思ってる」
「僕は特に学びたいものが無かったから就職したけど、大学へ行って何かを見つけるのもいいと思うけどな」
「うん……、本当はね、働いても大学でも何でもいいんだけど……」
「どういうこと?」
「この田舎から出て暮らしてみたいなって……、直くんの近くがいいなって思ったり……」
「うちの近くか……、でもまだ三年以上先の話だね」
「うん……、直くんの近くに住んだら会えるかなって思ったんだけど……」
「近くだったら時々遊びに行けるかもね」
「直くん、知ってる? 『いとこ』同士って結婚できるんだよ」
「調べたの?」
「うん……、直くん、彼女はいるの?」
「うん……」
いないと答えようかと一瞬迷ったけど、素直に答えてしまった。
「彼女いるんだ……、かわいい人? 写真持ってる?」
「写真は持ってないな、かわいいかどうかは……、どうかなあ……」
「直くん、帰ろ……」
帰りはしっかりと僕の腰に手を回し、顔を僕の背中に押し付けていた。家を出た時は走りながらずっと話をしてきたけど、帰りは無言だった。智子が顔を押し付けていた部分だけ僕のシャツが濡れていた。
家に着くと智子は自分の部屋へ走って入ったまま三〇分近く出てこなかったが、部屋から出てきた智子はいつもの明るい顔に戻っていた。
翌日も朝からいっしょに勉強したのですが、智子は集中力がまったく無く、心ここにあらずという感じがしました。
「あまり勉強をする気分にならないのなら、片付けて話でもする?」
「ううん、勉強するよ。私は受験生なんだから」
「でもね、気が進まない状態で勉強したって頭になんて入らないし、無駄な時間をすごすだけになるよ。だったら後で集中して勉強できるように、今は違うことをするのもいいと思う」
「うん、でも……」
「でも? どうしたの?」
「だって……」
「智子、片付けておいで。ちょっと家の周りを歩きに行こう」
「うん……」
智子はしぶしぶと言う感じで勉強道具を片付けに行った。
家を出て五分ほど歩き川の土手に並んで座ったが、しゃべりかけても上の空のような返事しかしない智子。
機嫌が悪いのかなと思っていたのですが、
「直くん、今の彼女と結婚するの?」
「結婚? 考えたことないよ。するかもしれないし、結婚に至らず終わるかもしれない。今はオートバイに乗って同僚と遊んだりするのが楽しいし、仕事は大変で本当に必死だから結婚なんて考えられないな。来年は昇格試験もあるから勉強も少しはしなきゃいけないしね」
「試験? 勉強しなきゃいけないの?」
「別に受けなくてもいいんだけど、試験に通らなきゃお給料が上がらないからね」
「彼女とはよくデートしてるの?」
「正直なところあまり会っていない、遊びと仕事のほうが勝ってるかもしれない。付き合っているというよりは、暇な時にちょっと会ってるだけって感じかもしれないよ」
「彼女がかわいそうよ、せっかく付き合っているのに、もっと大事にしてあげないと」
「僕も彼女も、本当に好きで付き合っているのではないのかもしれない、そう思うよ」
「そんないい加減な!」
「中学生に怒られちゃった……、でも本当のことを言うと、自分でも好きなのかどうかがわからないというか。友達よりはちょっと先の関係かもしれないけど、恋人と言うにはちょっと遠すぎる気がするんだよ。相手も同じような感じで、自分がしたいことを優先しているし。似た者同士で釣り合っているのかもしれないけどね」
「直くんはそんな付き合い方でもいいの?」
「仮定の話だけど、もしも本気で好きな人と付き合うようになれば全然変わってくると思う。オートバイに乗るよりデートを優先するはずだし、今は本心から相手のことを好きじゃないから、今くらいでちょうどいいのかなって思ってる」
「直くん、今、本当に好きな人っていないの?」
「今って言うか……、今まで本当に好きになった人っていないかも……」
「そうなの?」
「うん……、あえて言えば、昔は智子のお父さんが好きだったくらいかな」
「お父さん、今でも直くんのことがかわいくて、いい子だって言ってる」
「智子にそんなこと言ってるの?」
「うん、だから私は直くんって本当にいい人なんだって思ってるよ」
「ハハハ、騙されているんじゃない?」
「ううん、騙されてない。私もそう思うもん」
「でもさあ、下手したら僕と智子は兄妹になっていたんだよ」
「どういうこと?」
「智子と香織の女の子しかいないから、智子のお父さんは僕を養子にして跡取りにと考えていたことがあったみたいなんだ」
「直くんと兄妹……、ずっといっしょにいられるのはいいけど、でも……」
「智子のお母さんは僕ではなくて、弟を養子にしたかったみたいだけどね」
「徹くんと兄妹は嫌だな、それだったら直くんと兄妹の関係になるほうがいいけど……」
「ところで、智子は好きな人っているの?」
「うん!」
「同じ学校の子?」
「学校にもいいなって思う人はいるけど……、本当に好きな人は別……」
「そっかあ、実るといいね」
「実るかな? なかなか気付いてもらえないから……」
「待つだけじゃ伝わらないからね」
「そうよね……、そのうち勇気を出して言ってみるよ」
智子は少し元気が戻ってきたようなので、家に帰って勉強の続きをすることにした。
「直くん、どこか行ってたの?」
家へ帰ると香織が話しかけてきた。
「うん、その辺をブラブラとね、ピアノの練習は終わった?」
「午前の部は終了、昼からはまた先生の家へ行くよ」
「香織って忙しいんだね」
「でも好きだから忙しいとも思わないし、毎日楽しいよ」
「好きでやっているのならばいいよね、頑張ってね」
「頑張ってって言われなくても、これ以上頑張れないくらいに頑張ってるよ!」
最後は伯母そっくりな言葉で締められたけど、自分が好きで習っているピアノならばそれでいい。僕みたいに本当に今したいことが見つからず、とりあえずオートバイに乗っているだけよりはよほど良い。
香織がピアノのレッスンへ伯母といっしょに出かけた後、客間で智子と勉強の続きをしていた。午前中とは違って智子は少し集中力を取り戻してはいたが、
「直くん」
「何?」
「直くん、本当に今まで好きになった人っていないの?」
「いいなとか、かわいいなって思うことはあるけど、それ以上の気持ちにならないからなあ」
「直くんが好きになれる人、現れるかな……」
「そう言えば、好きな人は同じ学校じゃないって言ってたよね。顔を見たりはできるの?」
「年に一回も顔を見れないかな……。私は織姫様より好きな人に会えないから……」
「そうなんだ……。だったらよけいに、顔を見れた時に思いを伝えられたらいいね」
「うん……。でも、私のことなんて何も思っていないみたいだし……」
「それはどうだかわからないよ。智子のことを思っているけど何もアクションを起こさないだけかもしれないし、僕みたいに自分の本心さえわからない人間もいるし。今は特に何も思っていなくても、智子のちょっとした言動で気持ちが智子へ急速に傾くことだってあるしね」
「そうかな?」
「そうだと思うよ。それまでは全然気にしていなかった人なのに、ある日突然急に気になって惹かれたりもするから、何がきっかけで急展開するかわからないと思うしさ」
「直くんもこれまでにそんなことあった?」
「僕は今のところないなあ」
「直くんにも、そんな急な展開で人を好きになることって起きるかな?」
「こればっかりは分からないけど……、僕みたいな人間のほうが、急に身近な人を好きになることはあるかもしれないね」
「ホント?」
「たぶん……、でも、そのほうが深く真剣に好きになるかなとは思う……」
「そっかあ、じゃあ、私も期待して待っておこうかな……」
夕方まで話の傍ら少し勉強してすごしました。智子は朝とは違ってすっかり元気を回復して、活発な女の子に戻っていました。
智子が好きな人ってどんな人なのかな。スポーツ大好きで活発ではあるけど、自分を殺して一歩下がって振舞うなんてすごくいい女性じゃないか。まだ中三だけど、きっとみんなに好かれる女性になるよ。そんな女性に好かれる男って幸せ者だよなと、お風呂に浸かりながらぼんやりと考えていた。
「直くん、もう帰るの?」
翌日の朝、部屋で帰り支度をしていたら智子が話しかけてきた。
「うん、高速を使わずゆっくり下道で帰ろうと思ってるから、お昼前には出るつもりだよ」
「そうなんだ、今度会えるのは何年後かな……、織姫様みたいに毎年会いたいのにな……」
智子の目に涙が溜まりうるうるしていて、僕はその目に思わず引き込まれそうになる。まだ中学生の子供だと思っていたけどもう立派な女性なんだ。すぐに帰ろうと考えていたのに僕の心がそれを阻止するように、
「あの、智子、もし良ければだけど……、帰る前にオートバイで近くを一回りしない? もちろん嫌だったらこのまま帰るけど……」
頭ではまったく考えていなかったのに、なぜかそんな言葉を口にしていた。
「イヤなはずがないよ! 待ってて、着替えてくる!」
智子は大慌てで着替えて客間にやってきた。その様子を見ていた香織もやってきて、
「お姉ちゃん、どこか行くの?」
「直くんにオートバイに乗せてもらってくる!」
「いいなあ、香織も乗りたいのに……。直くん、乗せてよ!」
「香織を乗せると香織のお母さんに怒られちゃいそうだから……、ごめんね」
不服そうな香織を尻目に、僕は智子を後ろに乗せて少しだけオートバイを走らせた。今日は僕の腰に両手をしっかり回し、体をピタッと密着させてほっぺの辺りもくっつけているようだ。一〇分ほど走らせて山の中にある小さな公園に入った。夏休み中なので近所の子供たちが暑い中を走り回っている。
「直くん、ありがとう、帰る前に時間を作ってくれて。やっぱり直くんはやさしい、直くんだけは私のわがままも願いも全部叶えてくれる。でもまさかもう一度オートバイに乗せてもらえるとは思ってなかったから……、本当にうれしい、ありがとう、直くん」
「もう一度お馬さんごっこしようかと思ったんだけど、うれしくないよね」
「私はお馬さんごっこもうれしいよ、直くんが私のためだけにしてくれるんだもん。直くん、本当にやさしいね。私ね、直くんみたいな人に好きになってもらいたい……」
「僕みたいなのがいいとは思えないけど……、何かのきっかけで僕が智子にグッと惹かれて好きになっても、智子は迷惑に思うだけだろ……」
「そんなことはないよ! 直くんが好きになってくれたら……。羨ましい、直くんに好きになってもらえる女の人って……」
「いやいや、僕はどちらかと言えば優柔不断な男だから……」
「でも、私にいちばんやさしく接してくれるのは直くんだから、それにカッコいいし……」
「ほめても何も出ないよ」
「ほめているんじゃなくて、本心だから……」
「ありがとう、智子だけがそんな事を言ってくれる」
「直くん……」
「夕べお風呂に浸かりながら思ったんだけど、智子はまだ中三だけどみんなに好かれるいい女性になるだろうし、そんな智子にもし好かれたら、本当に幸せ者だなって思ったんだ」
「直くん……、私……」
「また智子に会いに来るよ。今までは祖母ちゃん、その前だと智子のお父さん、そして〝田舎〟に会いに来ていたけど、智子とすごした三日間は本当に楽しかったから」
「直くん……、私、直くんにまた会いたい、会いたいもん……」
「ホントに? よかった嫌われてなくて」
「私、直くんが……、直くんのことが……」
「うん?」
「ううん、何でもない。でも本当に、また直くんに会いたいから……」
智子を家まで送り届け、ゆっくりと国道を走り八時間ほどかけて家に帰った。なぜだか家に帰るまで、いや家に帰ってからも智子のことが気になって仕方がなかった。
よく「女の涙は武器」という言い方をするけど、智子の目に溜まった涙がうるうるしていて、その涙に僕の心を撃ち抜かれたのかもしれない。
『いとこ』としてはもちろん好きだけど、一人の『女性』としても智子に惹かれていく。
告白してフラれてもそれは仕方がないと思っているし、告白せずに後悔するくらいならばフラれるほうがはるかに良い。でももしも智子が僕のことを『親戚』『いとこ』としてだけ見ているとすれば、告白してフラれること以上に、
〝親戚なのに変な目で見られてる〟
なんて思われることが怖い。
それにフラれた後も親戚の関係だけは途切れずにずっと続くわけで、どんな顔をして会えばいいのかもわからない。
僕は社会人で智子は中学生。まだ中学生の子供に告白することは憚られるし、そもそも僕は智子のことが大嫌いだったはずだが。
ある日突然急に気になって惹かれたのかもしれない――。